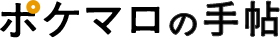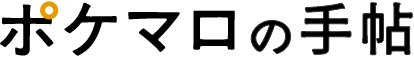永平寺 名古屋別院の「参禅会」に初めて参加させていただきました。
お寺の静かな空間で行う坐禅。決められた所作があり、普段私が習慣にしているマインドフルネス瞑想とはまた少し違った感覚で坐ることができた貴重な体験となりました。
今回は、その時に学んだ作法や、大まかな流れなどを振り返り、まとめました。
永平寺 名古屋別院「参禅会」に参加
| 場所 | 曹洞宗大本山永平寺 名古屋別院(坐禅堂) |
| 参加した日時 | 2024年9月 15時~16時 |
| 参加費 | 500円(初回は1,000円)※2024年時点の情報 |
永平寺 名古屋別院の参禅会は主に、毎月第2・第4土曜日に行われているそうです(※2024年時点の情報)
初めての参加者は、雲水さんによる坐禅指導を受けるため、開始時間の30分前に会場入りします。
受付

南側の立派な正門をくぐり、正面進んで(赤矢印)左手の建物に入って行くと、受付の場所があります。

事前予約などはなく、当日入口での受付です。
受付が済むと2階の広い和室に通されます。
この日は、参加人数がいつもよりも多かったそうで30人近くの方がいらっしゃいました。
20代くらいの若い方から、お年寄り、数人のグループで来られている方など、老若男女さまざまな人がいらっしゃいました。
坐蒲の持ち方
人数が集まり、時間になったら雲水さんから、まずは「坐蒲」の持ち方を教わります。
白い札が付いている部分を上にして、親指、人差し指、中指の3本の指を使い、両手で持ちます。
「坐蒲」を持ち、細い廊下を通って、「坐禅堂」の方へ歩いて向かいます。
坐禅堂への入り方
「坐禅堂」の入口の左側から入りますが、柱のある方の足(左足)から入堂します。
入堂したら、正面にみえる文殊菩薩さまに合掌低頭します。
中に入り自分の坐る位置へ進みます。この時、文殊菩薩さまの後ろを通ります。
坐る位置についたら「坐蒲」を畳の上に置きます。
基本的な作法

合掌
相手に対し敬意の念を表すための作法。手のひらを合わせ指を揃える。指先を鼻の高さに揃え、鼻から10cmほど離す。肩の力は抜く。

叉手
歩いている時や立っている時の礼法。左手は親指を包むように軽く握り、手の甲を外向きにしてみぞおち部分に当てる。その上から右掌を左手の甲に重ねる。
挨拶をする
隣位問訊
自分の坐る位置(壁側)に向かって合掌低頭(これは両隣の人への挨拶)。
次に、
対坐問訊
合掌のまま180度右回りをして向かいの人へ合掌低頭で挨拶。
再度180度右回りして壁側に向かいます。
坐る
畳一つを「単」と言うそうですが、ひとつの単に一人ずつ坐ります。(この日は人数が多かったので、ひとつの単に二人坐った人も数人います)
自分の「坐蒲」の形を整え白い札を向こう側にして置きます。
単の縁にある木の部分、修行僧が食事の時に応量器を置く場所の部分を「牀縁」と言うそうですが、その牀縁に体を触れないように、後ろ向きに坐蒲に飛び乗ります。(この飛び乗るのが足の短いわたしには大変でした。)

足を組み(結跏趺坐または半跏趺坐)、手を組みます。
手の組み方は「法界定印」と言って、右掌を下にしてその上に左手を乗せ、両方の親指の先を軽く合わせて卵型をつくるように組みます。
視線は1メートル先、45度の角度に落とします。目は閉じずに半眼。


坐禅開始
「調身調息調心」呼吸を調えます。
左右に体を揺すりながら、自分の中心軸をみつけます。
「止静鐘」という始まりの合図である鐘が3回鳴ります。
20分ほど坐禅します。
「警策の受け方」
坐禅中に集中できないと感じたら、自分から警策を受けることができます。
合掌をすると、右肩を2回軽く打っていただけるので、首を左前に傾けて右肩を空けるようにすると、警策を1回打っていただけます。受け終わったら合掌低頭します。
一度目の坐禅が終わり、休憩の意味合いとして、「経行」というものを5分ほどします。
これは道内を静かに歩いて行う歩く瞑想のようなものでした。
2回目の坐禅も20分ほど行いました。
放禅鐘(鐘1回)がなったら合掌低頭、組んでいる足を解きます。
このあと般若心経を皆で読経しました。
単から降り、出口右側へ進み、右足から退堂しました。
坐禅終了後
帰る際に、お寺の方から、手作りのお漬物や衣をつけて揚げたおまんじゅう、季節の野菜など、一人一つお好きなものをご自由にお持ちかえりください。とお土産もいただきました。
わたしは揚げ饅頭をいただいて帰りました。
体験して感じたこと
初めての座禅体験でしたが、坐禅堂に入ることができ、貴重な体験をさせていただけたことがとても良かったです。坐禅堂は薄暗く神聖な雰囲気が漂っていて背筋が伸びる気持ちにもなりますが、とても落ち着く空間でもありました。お寺のお坊さんは皆さんとてもやさしく親切に接してくださり、安心して体験することができました。
マインドフルネス瞑想との大きな違いは、細かく所作が決まっていることでした。一番わたしが難しいなと感じたのは目を閉じてはいけないことでした。畳の目をじっと見つめるのですが、なかなか集中が続かず苦戦しました。
様々な方とご一緒することで、他の人の息遣いが聞こえたり、姿勢を直している影が見えたりもしました。このことで自分がいかに周りの状況に影響されやすいかというのを再認識しました。
初体験ということで、さまざまなことが新鮮で周りに意識が向かいすぎていたのか、集中することができたのは、ほんの数分だったかもしれません。でも空間そのものに落ち着きと安心感があったので、不思議とココロは調ったように思います。
昨今、住環境を整えることは、メンタル面でも大切だと言われる意味が良くわかったように思います。
今回、初めての坐禅体験でしたが、とても楽しく学びの多い機会となりました。
また今後も機会を見つけていろいろな場所で参加してみたいと思います。
この記事で使用したイラストの他にも関連のイラストを、下のリンクから無料ダウンロードできます。よろしければご活用ください。