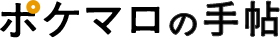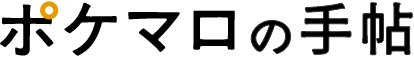お世話になっている方のご両親が営む柿農園から、今年も立派な次郎柿が届きました。
到着したばかりの柿。
せっかくなら!おいしいものを更においしくいただこうと思い、じっくりていねいに味わうことに。
まずは、切るところからマインドフルに
なるべく無駄のないように、ヘタのギリギリのところで丁寧に切っていきます。
皮を剥いていくサクサクとした音にも耳を澄ませます。
触った感触は、パリッとしてさっぱりとした印象。
硬めの柿が好きな我が家にはバッチリです。
では実食!(食べる瞑想)
いただきまーす!

シャキシャキ、パリッとした歯ごたえのある食感。
口に入れた直後すぐには甘みを感じませんが、よくよく噛んでいくうちに、舌の上にじわーと甘みが広がっていきます。
食べ終わった後も長い間、口の中に甘みが強く残ります。
水分が少なめなので、その分甘みが凝縮され、強く感じるのかなぁなんて思いました。
(今回はやりませんでしたが、食材の香りをかいでみるのも良いかもしれません)
とってもおいしかったです!
次郎柿の発祥について
なんとなく知りたくなったので、次郎柿の発祥についても調べてみました。
静岡県森町の公式サイトによると
甘柿の代表種「次郎柿(治郎柿)」は、当地遠州森町原産で、その原木は町民をはじめ多くの方々に可愛がられ、今も大切に守り育てられています。
次郎柿の誕生は、江戸末期の 弘化(こうか)年代(1844年~1847年)に 森町村 (もりまちむら)五軒丁(ごけんちょう )の百姓「治郎(松本)」が太田川の川原で柿の幼木を見つけ、これを持ち帰り自宅に植えたのがはじまりです。その後、明治2年(1869年)の火事により焼失。しかし、翌年に芽を出し成長して、数年後には再び実をつけました。ところが、その実は焼失前に比べて肉質はきめ細やかで 甘味(あまみ) も 豊潤 (ほうじゅん) 、加えて種も少なくとてもおいしい柿でした。他に比類無き卓絶する良品種であったと伝えています。
当時人々は、「治郎さの柿・じんろうさの柿・じん郎柿・治郎柿」と呼称し、戦後は「次郎柿」と書かれるようになりました。
※引用元:静岡県森町「文化財」ページより
今でも当時の原木が県指定の天然記念物として、町の人たちの手で大切に守られているんですね。
江戸時代の一本の柿の木からずっと繋がって、今こうしてわたしがおいしく次郎柿を食べることができているんだなぁ…と思うと有り難みが一層増す気がします。
ちなみに、わたしが今回食べた次郎柿は「浜松市浜北区大平」というところのものです。
静岡周辺の地域の人達が愛してきた次郎柿。
育てている農家さんにも思いを馳せつつ…味わっていただくことができました。
ごちそうさまでした!
まとめ
こんな感じで毎日の食事の時間、最初の一口目だけでもマインドフルに食材と向き合う時間を意識的につくってみるのって良いかもしれません。
たった数分間の毎日の積み重ね。
自分の反応や感情に気づく練習になると信じてこれからも思い出したときに実践していこうと思います。
何よりおいしい物が、よりいっそうおいしく味わえるのなら、こんなうれしいことはありませんよね。
よかったら、試してみてください。
読んでいただきありがとうございました!